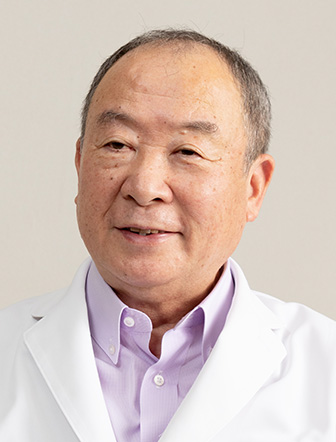二日酔いのメカニズム
二日酔いは酒の飲みすぎが原因であることは明白です。しかし、二日酔いの症状が何故起きるのかについてはほとんど解明されていません。有力な説として、軽度の離脱症状・ホルモン異常による脱水や低血糖・体の酸塩基平衡の不均衡・炎症反応・アセトアルデヒドの影響・酒に含まれるメタノールや不純物などが挙げられています。しかし最も的を射ているのは、単一要因ではなく既述の要因または未だ不明の要因が複雑にからみあって二日酔いが生まれるという説明でしょう。
1. 二日酔いとは
二日酔いの歴史は古く、すでに旧約聖書にその記述が見られます。しかしその長い歴史にもかかわらず、二日酔いの定義や診断基準などは未だ示されていません。症状は、頭痛・胃腸症状・睡眠障害・感覚や認知の障害・うつ気分・自律神経症状など様々です[1]-[3]。
2. 二日酔いのメカニズム
二日酔いは酒の飲みすぎが原因であることは明白です。しかし、二日酔いの症状がどのようなメカニズム(発症機序)で起きるかについては、不明な点が多いのが現状です。下記に発症機序を説明しうる要因を列挙しました[2][3]。
二日酔いの促進要因[2][3]
- 軽度の離脱症状(「アルコールと依存」参照)
- ホルモン異常・脱水・低血糖・その他
- 酸塩基平衡の不均衡や電解質の異常
- 炎症反応の亢進
- 睡眠や生体リズムの障害
- アセトアルデヒドの蓄積
- 胃腸障害
- メタノール
- 酒に含まれる不純物(congener)
- その他
まず、二日酔いはアルコール依存症に伴う離脱症状の軽症・短時間版という捉え方があります。確かに二日酔いに見られる自律神経症状は離脱症状のそれに類似しています。しかし脳波検査によると、離脱時期には速波化するのに対して、二日酔い時には徐波化する(両者で正反対のパターンをとる)ことから、この類似に意義を唱える者もいます[2]。
酩酊状態から二日酔い状態になっていく間にホルモンの分泌状態が大きく変化するものもあります。尿量を下げる抗利尿ホルモン、尿の排泄や血圧の調整に関係するアルドステロン・レニンなどがこれに当たります。
例えば抗利尿ホルモンは、酩酊時にその分泌が少なくなるため、尿量が増えて体が脱水傾向になります。二日酔い時には逆にその分泌が増加します。抗利尿ホルモンのこの変化量は、二日酔いの重症度と関係があると示唆されています。
またこれらのホルモンほど明らかではありませんが、糖代謝に関係するインスリンやグルカゴンの分泌も変化します。これらの変化に伴う脱水や低血糖状態が、二日酔い症状の一部をなしています。
二日酔い状態では、体の酸塩基平衡(酸性/アルカリ性バランス)が酸性に傾き、この程度が二日酔いの重症度と関係があることが指摘されています。また二日酔い状態では、サイトカインなどの炎症反応のマーカーが高値になることも報告されています。これは「消炎鎮痛薬が二日酔いに対してある程度効果がある」という根拠になっています。
一方で、以前から本命とされていた、血中アセトアルデヒドが二日酔いに関係していることを示すデータはほとんどありません。実際、二日酔い状態にあっても、血中にアセトアルデヒドが検出されることは稀です。しかし、フラッシング反応を示す非活性型ALDH2を有する人は二日酔いになりやすいことが報告されています[4]。もしかするとアセトアルデヒドそのものではなく、その後遺症が関係しているのかもしれません。その他、メタノール・胃腸症状・酒の不純物なども原因とされています。
以上を踏まえ、最も的を射ているのは、単一要因ではなく既述の要因または未だ不明の要因が複雑に絡みあい二日酔いが生まれる、という説明でしょう。二日酔いになるほど飲まなければよい話ではありますが、さらなる研究が必要なことはいうまでもありません。
(最終更新日:2025年9月1日)
参考文献
- Swift R, Davidson D.
Alcohol hangover: mechanisms and mediators.
Alcohol Health Res World 22: 54-60, 1998. - Wiese JG, Shlipak MG, Browner WS.
The alcohol hangover.
Ann Intern Med 132: 897-902, 2000. - Prat G, Adan A, Sánchez-Turet M.
Alcohol hangover: a critical review of explanatory factors. Hum Psychopharmacol Clin Exp 24: 259-267, 2009. - Yokoyama M, Yokoyama A, Yokoyama T et al.
Hangover susceptibility in relation to aldehyde dehydrogense-2 genotype, alcohol flushing, and mean corpuscular volume in Japanese workers.
Alcohol Clin Exp Res 29: 1165-1171, 2005.