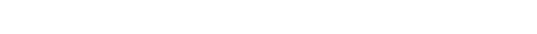- TOP
- 健康寿命をのばそう!アワード
- 第13回健康寿命をのばそう!アワード 審査のポイント

第13回
健康寿命をのばそう!アワード
募集期間:
令和6年7月1日(月)~ 8月31日(土)
評価委員による審査のポイント
評価委員の先生方より「健康寿命をのばそう!アワード」審査のポイントを伺いました。

武見ゆかり先生から見た審査のポイントはここ!
女子栄養大学 副学長
ポイント1参加者(利用者)の行動変容を促す工夫や仕掛け(ナッジ等)があるか
人々の行動変容を促すには、知識を得て理屈を納得してもらって行動変容を促す方法(従来の教育)と、知らないうちに望ましい行動へと誘導する方法(ナッジ)があります。後者の工夫がある取組を期待します。
ポイント2教育支援と環境整備の両方を組合せた取組となっているか
教育的なアプローチでは、効果は関心のある層に限られる傾向があります。すべての対象者に届くような環境整備の取組と組み合わせることが重要です。食生活では、対象に提供される食事・食品そのものを健康的なものに変えること、これがポイントです。
ポイント3他組織、他地域への波及が見込める取組か
どんなに効果のある取組でも、特別な条件が整わないと実施できない取組では他組織・他地域への波及が見込めず、社会全体の健康寿命延伸につながりません。どのような条件が整えば他組織、他地域でも実施可能なのか説明してくださると良いと思います。

津下一代先生から見た審査のポイントはここ!
女子栄養大学 特任教授
ポイント1取組や活動の目的を明確に示し、それを解決しうる方法を選択しているか
対象集団の健康課題や解決すべき事象を把握し、それに対して科学的な根拠のある方法を検討しているか、ターゲット層を意識した実効性のある方法をとっているかを確認します。長年積み重ねてきた活動を客観的に評価し、新たな視点や意義を見出した取組も重要と思います。
ポイント2参加者が主体的に活動しているか、住民や関係者などコミュニティの結びつきが進んでいるか
参加者や関係者がやらされ感でなく、健康づくりの大切さを実感して楽しんで参加していること、参加者の声や変化をとらえて取組を継続的に改善していることが重要です。この取組や活動を通じてコミュニティの結びつきが深まる取組について高く評価します。
ポイント3新たな健康課題、新たな方法を模索しているか。
コロナ禍の影響や健康課題の変化にともない、健康づくりにも新たな視点・方法論に関心が集まっています。新たな生活様式における健康づくりのヒントや実施方法の工夫など、新たな視点・方法を取り入れた取り組みを評価します。

中村正和先生から見た審査のポイントはここ!
公益社団法人 地域医療振興協会 ヘルスプロモーション研究センター センター長
ポイント1先進的・先駆的な取組であるかどうか
既成の事業にとらわれず、新しい発想が盛り込まれているか、目新しい手法が使われているかをチェックします。今後の事業の継続性や発展性についても合わせて審査します。
ポイント2計画的に企画・実施され、効果検証がされているかどうか
PDCAに基づいて事業の企画から評価に至る一連のプロセスが計画的にかつ手順を踏んで実施され、効果が確認されているかどうかをチェックします。取組の期間が浅く、アウトカム指標では評価できない取組については、プロセス評価の結果から健康寿命の延伸に照らして効果が期待できるかどうかを審査します。
ポイント3好事例としての普及可能性があるかどうか
好事例として、他の自治体や企業、団体への普及が期待できるかどうかについて審査します。また、普及した場合にどの程度の効果や社会的インパクトが期待できるかという視点でも審査します。

杉山雄大先生から見た審査のポイントはここ!
国立研究開発法人 国立国際医療研究センター 研究所 糖尿病情報センター
医療政策研究室 国際医療協力局 グローバルヘルス政策研究センター(iGHP)
ポイント1誰一人取り残さない健康づくりを目指しているか
メッセージの届きにくい対象にアプローチすること、健康格差を縮小することは健康日本21(第三次)でも重視されています。大変難しい課題であることは存じておりますが、個人へのエンパワメント、社会環境の整備を通じた、インクルージョンの理念達成に向けた姿勢と進捗を審査します。
ポイント2効果を高める努力と効果の測定、改善活動を行っているか
実効性をもつ取り組みを推進するには、効果の見込まれる介入を選び行った上で、あらかじめ設定した指標をもって効果を測定して評価し、課題を抽出して更なる改善に繋げることが重要です。これらのPDCAサイクルが可視化されたプレゼンテーションを期待します。
ポイント3人・社会と調和したICTの利用がなされているか
洗練されたICT技術は介入の効果を高め、効果測定を効率化するなどの長所があります。特に人・社会と調和したICT利用は、広がりと継続性を高めます。具体的には、利用者ニーズに応じたカスタマイズや保健人材の介在、コミュニティ参加を促す仕組みが重要であり、このような工夫をこらしたICT利用の実践に注目します。